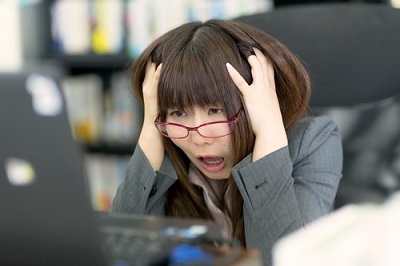司法試験予備試験に限らず、難関試験に短期間で合格しようとするならば、テキストや基本書など書籍を徹底的に絞り、繰り返すことが大切です。
うちのローの教員が言うてた「基本書は手を出しすぎるのではなく、これと決めた一冊を繰り返して読むことを薦めます」
— あずき (@AzukIzororuna) December 21, 2024
まさにこれ。これと決めた一冊を読みまくって、論点について6〜7割くらいの精度での説明を何も見ずに説明できるようにするのが大事やと思います
(中略)
司法試験対策においても同様に、「量の増加」が「質の低下」を招く場合があります例えば、過度な参考書の購読
現在では、司法試験対策に有用とされる書籍が多く出され、合格者や受験指導者が各々、「これは良い」などと推奨しています
受験生の中には、それらが全て必要と考え、あれこれ手を広げてしまう人も少なくありません
しかし、これには以下のような問題があります
1.情報過多
多くの参考書を読むことで、情報が過剰になり、重要なポイントが見えにくくなる
また深い理解より表面的な浅い知識が増えることになる2.時間不足
多数の参考書を読むことに時間を費やしすぎ、自ら考える時間や過去問などの演習に割ける時間が減少する3.混乱
異なる参考書間での内容の違いやアプローチの違いにより、混乱が生じ、知識が断片的になりやすい
そして、その解決のためにまた別の参考書に手を出すという悪循環合格のためにと、多くの参考書を手にしたことが必ずしも効果につながらず、そればかりかかえって合格を遠ざけてしまうことにもなりかねません
「量の増加が質の低下を招く」一例と言えるでしょう
そうならないために、以下の点に注意すべきです
1.教材・テキストの厳選
必要最低限の参考書を選び、それらを繰り返し読むことで、深い理解を得ることを優先する
例えば、受験指導校で提供されるテキストや推奨される基本書を中心に使用します
これで十分に合格ができます2.計画的な学習
学習段階に応じた適切な学習を進める
それぞれの段階で何をすべきかを明確にする
例えば、基礎講義は細かい知識や応用的論点に拘らず、全体像と重要なポイントに的を絞る学習であることを忘れない
これにより、過度な量に振り回されず、効率的な学習が可能になります3.復習と問題演習の重視
参考書を読むことに時間を費やすのではなく、基礎問題や過去問の演習にしっかりと時間を割く
問題演習を通じて実践力を養い、知識を定着させます試験に合格する力を身につけるためにはある程度の量をこなすことが必要です
そこでの「量」とは深めるため、実践力を身につけるためにくり返す「量」ですしかし、むやみに広げて「量」を増やすことは、むしろ「質」を落とすことになります
量に頼りすぎず、質を重視した効率的な学習を心がけることが司法試験対策として重要です
引用 X
元のツイート(投稿)はこちら↓
【「量が質に転化する」ということと「量の増加が質を低下させる」ということ】
— 高野泰衡@加藤ゼミナール・司法試験予備試験講師 (@YasuhiraTakano) December 20, 2024
「量が質に転化する」
一般論としてよく言われることです
司法試験対策においても、それはあてはまります
まずは、一定の量をこなすことが、合格の力(質)を身につけるために不可欠です…
短命な選手に共通する“逃げ”の姿勢「ひとつの事をやってられない」
これは司法試験予備試験だけの話ではありません。プロスポーツの世界でも同じでした。大切なのは「ひとつのことを続けること」です。
短命な選手に共通する“逃げ”の姿勢「ひとつの事をやってられない」
頂点を目指して共に戦う同僚は、限られた枠を争うライバルでもある。チーム内には“序列”があり、その底辺にいる選手たちが戦力外になる。「仮にプロ生活が10年あるとしたら、最初の3年でどこまで基本の土台ができたかで決まる。その後の4~6年目である程度勝負できないと早く終わる」。経験則からそう語る森野氏は、わずか数年でプロ人生の岐路に立たされる選手を「日々の練習を見ていたら分かる」と言い切る。「ひとつの事をやってられない。何かすぐに変えてみようとする。探究心があるという見方もできるかもしれないけど、何かを極めようとはならない」
壁にぶつかると、まず目先を変えてみる。懸命な試行錯誤にも見える一方で、安易な“逃げ”につながるという。「長くやれるのは、基本があるから。吉見(一起)や大島(洋平)だってそう」。35歳を迎えた今でも衰えを感じさせない竜の安打製造機や、今季限りで引退した黄金期のエースを引き合いに、“長生き”の秘訣を説く。
これは核心をついています。
結果の出ない受験生の方ほど不安になると、すぐに違う基本書や演習書に手を出しがちですが、これはダメ。
まずは「一つのことを続けること」。これが鉄則であり、司法試験(予備試験)の合格の決め手です。